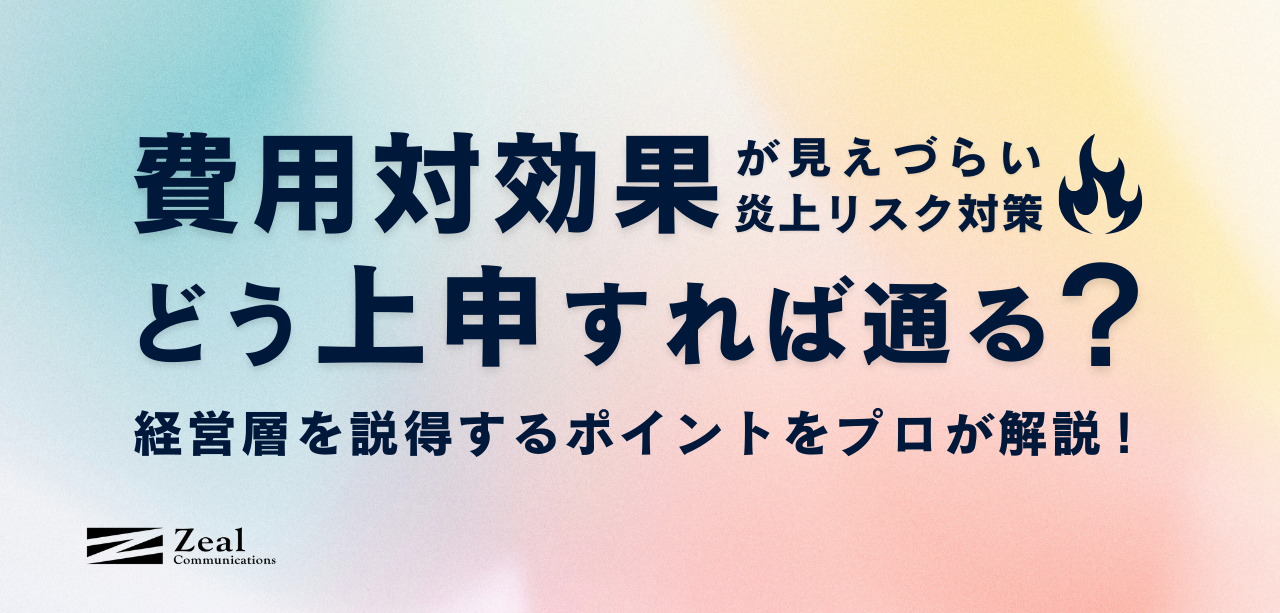「SNSリスク対策、やった方がいいとは思うけど、これって本当に費用に見合うのか?」そんな疑念の声は、どの企業でも聞かれます。特に、グループ会社の総務部門や広報部門が「本社としての一貫した体制づくり」を検討する際、最初にぶつかる壁が「経営層への説得材料不足」です。
SNSリスクは、火がついたときには手遅れになりやすく、しかも多くの場合、“炎上しなかったこと”の効果を証明するのは困難です。だからこそ、上申時には費用対効果を定量的に証明しようとするのではなく、別のアプローチで説得力を高める必要があります。
目次
組織的なデジタルリスク対策がなければ、結局自分が炎上対応に追われることに
昨今の炎上傾向を見ても分かるように、リスクは一部の広報部門や個人のSNSリテラシーでは防ぎきれません。 にもかかわらず、リスク対策は「とりあえず」で後回しにされがち。いざインシデントが起きたときには、本来SNSに関与していなかった総務や法務に火の粉が飛ぶことも少なくありません。
特にコーポレート部門の課長・部長クラスでは、「そろそろ何かしらの体制を作らないと…」という感覚を持っていても、行動に移せていないケースが多いようです。その背景には、「リスク対策の重要性をどう伝えれば、経営層の理解が得られるのか分からない」「自社潜むリスクを調査したいが何から始めればよいか分からない」といった情報不足が大きく影響しています。
上申が通るかは「正しさ」よりも「組織にとっての合理性」
上申の際に陥りがちなのが、「正論をそのまま伝える」アプローチです。 もちろん、リスク対策の必要性は論を待ちません。しかし、それだけでは組織の意思決定者は動かないのが現実です。必要なのは、「なぜ今やるべきか」を組織の課題や文脈に結びつけて語ることです。
たとえば、
- 自社の従業員がSNS上でトラブルを起こす可能性がある業態か?
- 既に近い業界で炎上事例が起きているか?
- 監査や上場企業としての対外的説明責任に影響があるか?
こうした切り口から「自分たちにとっての火種」がどこにあるかを見極め、その火種を“具体的な損失”や“業務負担”として可視化することが鍵になります。必要であれば、他社事例や簡易診断のような素材を使い、「いま放置すれば、こうなる」という未来像や、「“デジタルリスク対策をしていた場合”と“していなかった場合”」で比較し提示するのも効果的です。
デジタルリスク対策実施・未実施の比較
| 対策済の場合 | 未対策の場合 | |
|---|---|---|
| 初動対応 | ・エスカレーションフローに沿って即対応 | ・混乱 ・責任の押し付け合い ・炎上拡大 |
| 被害拡大 | ・的確な一時対応で早期鎮静化 | ・不適切な炎上対応で二次炎上 |
| 信頼維持 | ・誠実な対応でブランド保全 ・対応次第で称賛 | ・メディアやSNSで批判殺到 ・レピュテーション損失 |
| 対応 | ・企業としての見解発表 ・謝罪対応 | ・度重なる謝罪対応 |
| 損失 | ・最低限の損失で早期収束 | ・数百~数億単位の売上損失 ・ブランド毀損 ・人材流出 |
上申を成功させるための「事例づくり」のススメ
実際に成功している企業の多くは、いきなり数百万円の予算を獲得したわけではありません。 小さな成功体験の積み上げが、「この分野に予算をつける理由」を社内でつくってきたのです。
たとえば、
- まずは一部門だけで研修を試行し、満足度やアンケート結果を添えて報告
- モニタリングをスポット的に導入し、課題の顕在化を資料化
- ガイドラインのドラフトだけ先行作成し、社内展開を想定して議論喚起
これらの“小さな成果”を積み上げながら、段階的に上申するという方法は、特に予算獲得が難しい企業においては有効です。
ノウハウや材料が不足しているなら、まずは「情報収集」としての動きから始める
「資料を作ろうにも、何を調べればいいか分からない」という声もよく聞きます。
そうしたときは、まず社外に目を向けることも重要です。 セミナーや他社事例の調査、簡易診断のような無料ツールなどを活用することで、「自社が何をやれていないのか」「他社と何が違うのか」を相対化できます。
実際、当社でも「まずは簡易診断してほしい」「事例をもとに説得材料を集めたい」といった相談を受けることが多くあります。その結果として、「これなら通せそうだ」という社内での合意形成につながったケースも複数あります。
資料の説得力ではなく、文脈と火種の特定から始めよう
リスク対策において「費用対効果」という言葉は、時に無力です。
なぜなら、炎上が「起きていないこと」こそが成果だからです。
だからこそ、上申時には“何をすれば、誰のために、どのような成果が見込めるのか”を、自社の課題と結びつけて語る必要があります。そしてそれは、情報や他社事例を集め、社内の火種を特定することから始まります。
上申や体制づくりを成功させた企業の事例をまとめた資料を公開中です。自社にデジタルリスク対策を取り入れるためのヒント、上層部を動かすための説得材料としてもご活用いただけますので、お気軽にダウンロードください。