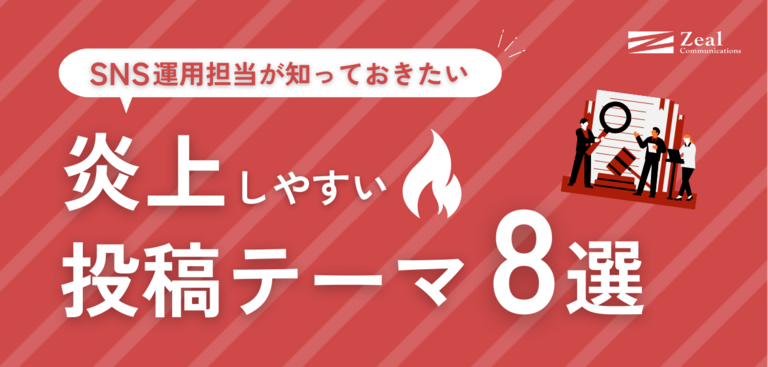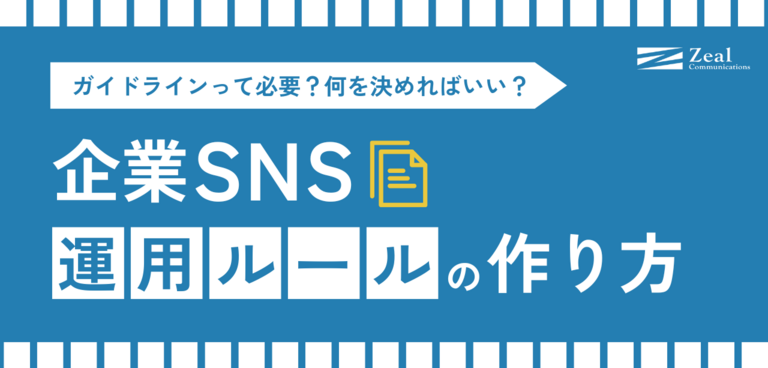SNSを活用する企業が増え、従業員のほとんどがSNSを使うようになった現代。SNSの影響力や拡散力はすさまじく、ひとたびSNS上で炎上が起こってしまうと収拾が付かなくなるケースも多々あります。
そこで本記事では2025年に起きた最新のSNS炎上事例を取り上げ、2026年企業としてどのようにSNS炎上と付き合っていくべきか、その対処法・対策までをわかりやすく解説していきます。
弊社では毎月炎上事例やSNS炎上対策・対応ノウハウに関するセミナーを開催しています。ぜひ本記事と併せてセミナーもご活用ください。
目次
企業の最新SNS炎上事例12選【2026年最新】
今回は2025年に起きた炎上事例12選をご紹介します。
SNSでの不適切表現による炎上
【事例1】大手食品メーカーでの不適切投稿
大手食品メーカーが運用するXアカウントにて「冷やし中華なんてこれだけでも十分美味しいです」といったテキストとともに具なしの冷やし中華の写真を投稿しました。自社製品をPRするための投稿だったにも関わらず「家事の苦労を軽んじている」といった批判が集まり炎上する事態となりました。ちょうどこの時X上では、「そうめんや冷やし中華を作ることは重労働か」という論争が起きており、その真っ只中で投稿した内容であったために炎上が悪化してしまったと考えられます。
【事例2】大手弁当チェーンの不適切投稿
大手弁当チェーンが運用するXアカウントでエイプリールフールに「米の価格高騰を鑑みて、全国のほっかほっか亭全店でのライスの販売を停止します」という実在の取締役名義の文書を掲載した投稿を行いました。企業側としてはエイプリールフールの“ネタ”として投稿したものでしたが、SNS上では「米不足が問題になる中不謹慎だ」などのコメントが殺到し、会社へも電話やメールで問合せが数十件届くなど大きな影響がありました。結果、当日中に同社はSNSにて謝罪を行う事態となりました。
従業員・顧客による炎上(バイトテロ・迷惑動画)
【事例3】大手回転寿司チェーンでの迷惑動画炎上
大手回転寿司チェーンに来店した女性客がレーン上の寿司を素手で触ったり、卓上の醤油差しから直接醤油を飲んだりする様子を動画で撮影し、SNS上に投稿を行ったことで拡散され炎上しました。同社は公式サイトで声明を発表し、当該店舗での全商品の入れ替えとこれまで通りお客の入れ替わりのたびに備品の交換と消毒を行っていると説明を行いました。問題となった動画はZ世代を中心に人気の高まる「BeReal」で撮影された動画であったことが特徴として挙げられます。
【事例4】大手コーヒーチェーンでのバイトテロ
大手コーヒーチェーンのアルバイト従業員が勤務時間中に不適切な言動を動画で撮影し、SNSに投稿されたものが拡散し炎上しました。同社は騒動の数日後に声明を発表し、事態への謝罪と、対象者を特定し懲戒処分にしたとの対応を説明しました。上記の回転寿司チェーンの事例と同様、BeRealで撮影した動画がXによって拡散されるという炎上パターンであり、2025年下半期にはこのケースが頻発しました。「1日1回ランダムな時間に通知が来る」「通知が来たら2分以内に投稿しなければいけない」という独自のルールによってバイトテロが起きやすくなっているとも言えます。
商品やサービスの不備による炎上
【事例5】大手飲食チェーンでの害虫・害獣混入問題
大手飲食チェーンのある店舗で提供された商品の中に害獣が混入していたとして画像とコメントがGoogleマップの口コミに掲載されたことで炎上しました。画像のインパクトが強く、SNSで瞬く間に拡散され、会社は謝罪を行った上で全店舗を一時休業するという対応を行いました。しかしこのレビュー投稿が行われたのが混入事案発生の約2か月後だったことから、事実を隠蔽しようとしたのではないかとさらに炎上が起こりました。
【事例6】人気ファッション誌での不適切表現
人気ファッション誌内で「看護師の院内不倫」をテーマにした着回しコーデを紹介する特集が「医療従事者をバカにしている」「下品すぎる」などの批判が集まって炎上しました。炎上を受け、ファッション誌は謝罪を行う事態となりました。
【事例7】ラーメンチェーン店での店舗トラブル告発による炎上
ラーメンチェーン店に訪れた女性客がXに「他の人のマシコールは普通で私だけ手でギチギチに押し込んでたのきしょすぎ」「食べ物で遊ばれた」などと投稿し、SNSで拡散されて炎上する事態となりました。これを受けて店側の公式Xでは「従業員ヒアリングと店内カメラ確認の結果、投稿内容は事実と異なることが判明しましたので報告させていただきます」と投稿。これに対して「カメラ映像と音声がないと事実と異なりますって言われても判断出来ない」「流石に店員の言い訳だと思うけど」などのコメントが集まりました。
【事例8】アパレルブランドでの店舗トラブル告発による炎上
人気アパレルブランドの公式Xが「ブランドの利用に関するお願い」と題し、一部のお客によるカスタマーハラスメントがあったと報告しました。今後これらの行為が確認された場合には法的措置も含めて厳正に対処する、と説明を行いましたが、この声明文を受けてSNS上では批判の声が殺到しました。以前からこのアパレル店は「スタッフの接客態度が悪すぎる」等の声がSNSやGoogleマップ上に多数寄せられていたため、このカスハラ声明を機にSNS上では次々と従業員の不手際が告発されました。結果このアパレルブランドは謝罪文を発表することになりました。
広告・CMでの不適切表現による炎上
【事例9】大手食品メーカーのアニメCMでの不適切表現
大手食品メーカーが公表したアニメCMが「性的である」とSNS上で炎上が起きました。CM動画の内容はアニメ調で若い女性が同社商品を食べるシンプルな内容ですが、頬を赤らめているシーンや口元がアップで映されているシーンなどが性的であると感じたユーザーが一定数おり、「気持ち悪い」などの声が集まりました。しかし一方で「何が悪いのかわからない」「過剰に反応しすぎ」などの声も多く、メディアがいかにも炎上しているかのように取り上げる「非実在型炎上」だとする意見も上がりました。この騒動に対しこの企業は「静観」を貫きました。物議をかもしたものの結果的に擁護派が多く、静観の姿勢もむしろ評価されました。
【事例10】人気アプリ運営会社の広告動画での不適切表現
人気アプリ運営会社が公開した広告動画に批判が殺到しました。動画は、“鉄道オタク”の社員が落とした鉄道模型を通りかかった同僚が足で踏んでバラバラになってしまう、というもの。これに対し「どんな倫理観ならこれを世に出せるんだ?」など批判の声が殺到し、炎上しました。これを受け同社は公式SNSにて「配慮が欠けていた」と謝罪を行いました。
【事例11】大手文具メーカーでの生成AIによるポスター表現
スペインで開催されたイベントで大手文具メーカーが使用した販促用ポスターに対し「画材の会社がAIでポスターを作ってるなんて」と来場者がSNS投稿し、一時炎上する事態となりました。SNS上では「画材屋さんはさすがに使わない方が良い」「AIを使うことに抵抗はないが、AIに丸投げしてチェックを怠ったことが問題」などの声が上がりました。これに対し同社は公式声明を発表。グループ傘下の販売子会社が生成AIを使用して制作していたことを確認し、チェック体制を強化し再発防止に努めると説明しました。
【事例12】大手物流会社のPR動画での不適切表現
大手物流会社の配達員の男性と荷物を受け取る女性の玄関先での様子を描いたPR動画が炎上しました。配達員がサインをもらおうとすると、女性が「すっぴんを見られたくない」とドア越しに慌てるというシーンに対し、「女性をバカにしている」「すっぴん=恥という意識を助長している」などの声が集まりました。批判の声を受け、同社は動画を削除して謝罪を行う事態となりました。
企業のSNSが炎上する原因
ここまで直近2年で起きた企業のSNS炎上事例をご紹介してきました。では、SNS炎上が起こってしまう原因はどこにあるのでしょうか?事例を踏まえながらSNS炎上につながりやすい5つの原因をご紹介します。

1. 公式SNSでの不適切投稿
1つ目は公式SNSでの不適切投稿です。上記の炎上事例の中でもご紹介したように、SNS運用担当者のリテラシー不足やプライベートSNSとの切り分けが出来ていないこと、また社内でのコンテンツ確認不足などが原因で起こります。また投稿内容だけでなく、その時のSNS上のトレンドや時事などの文脈で炎上につながるようなケースも増えています。SNS運用が属人化している企業やSNS運用業務にリソースをあまり割けない企業で起こりやすくなっています。
以下の記事では、特にSNSで注意が必要な炎上しやすいテーマ8選を取り上げていますので、ぜひチェックしてみてください。
2. 広告・キャンペーンでの不適切な表現
2つ目は広告・キャンペーンでの不適切表現です。先ほどの炎上事例でもご紹介しましたが、駅などの広告やテレビCMなどでの表現もSNS上で議論となって炎上に発展します。これらの炎上も社内でのコンテンツの確認不足や、担当者のリテラシー不足などが原因で起こります。様々な視点からクリエイティブチェックを行い、不快に感じる表現ではないか入念にチェックを行う必要があります。
3. 従業員による不適切投稿
3つ目は従業員による不適切投稿です。2025年も再び世をにぎわせた大手飲食チェーンでのバイトテロですが、従業員による悪ふざけやいたずらをSNSに投稿し、炎上するようなケースは時代が変わっても、プラットフォームや炎上の形を変えながら発生し続けています。投稿をした本人も個人情報の特定や誹謗中傷を受けることになり、企業側にとっても大きなブランド毀損となります。
4. SNSでの告発
4つ目はSNSでの告発で、従業員や顧客によって企業の問題や店舗・商品のトラブルがSNSで公に告発されて炎上するケースです。昨今はInstagramのストーリーズやBeRealなどクローズドなSNSの中で気軽に投稿できてしまうようになりました。従業員の告発の場合、社内の内部告発制度が機能していないことや相談先がないことが原因として考えられます。また顧客の告発の場合、店舗での従業員の対応が不十分だったり、その後のフォローが不足していることで不満がそのままSNSに投稿されてしまうこともあるため、トラブル対応のマニュアルを整備する、従業員に浸透をさせるなどの対策が必要です。
5. 商品やサービスの不備によるトラブル
5つ目は商品やサービスの不備によるトラブルです。画像とともに投稿される不備やトラブルは特にインパクトが強いため、SNS上で拡散・炎上しやすい傾向にあり、内容によっては大きなブランド毀損につながります。上記でご紹介した炎上事例の中には、消費者側の不備により害虫が混入していた事案もあり、企業にとって非のないトラブルの可能性もあります。また最近は生成AIを使った偽画像が出回っているケースもあり、投稿されている画像や内容が本当に事実であるかどうかを見極める必要もあります。
SNS炎上による企業への影響
ではこのようなSNS炎上が起こった時、企業にはどのような影響があるのでしょうか?3つご紹介します。
1. 不買運動や風評による売上減少
まず1つ目は不買運動や風評による売上減少です。特に商品やサービスの不備によるトラブル炎上が起こった場合、不買運動が起こるケースが多々あります。不買運動による短期的な売上減少だけでなく、ブランドイメージの低下から長期的に売上が減少する可能性もあります。
2. ブランドイメージの低下
SNSは拡散力が強く、さらにネガティブな情報ほど拡散されやすい傾向にあります。後ほどご紹介しますが、特に昨今はSNSの拡散スピードが増しており、多くの消費者にネガティブな印象を与えることでブランドイメージが悪化してしまいます。
3. 採用活動への影響
内部告発によるSNS炎上などは採用活動への影響や、人材流出につながる可能性があります。上記事例でもご紹介したような内定者辞退はもちろんのこと、次年度の応募者減少につながるケースもあります。検索エンジンで企業名を検索した時に、炎上のネット記事が出てきたり、採用サイトでネガティブな口コミを書かれてしまったりすることで、応募をためらったり、内定承諾を迷ってしまったりする可能性もあります。
企業のSNS炎上が起こるまでの流れ
ではここで、SNS炎上が起こるまでの流れを整理していきます。

SNS炎上は、問題となる投稿が発信されてから、共有やリツイートをされることで徐々に拡散していきます。昨今では「炎上系(暴露系)インフルエンサー」と呼ばれるSNS上で影響力を持つユーザーが投稿を行うことで、これまで以上に爆発的に拡散されるようになりました。炎上を1つのエンタメとして楽しむようなカルチャーも生まれ、これまで以上に拡散スピードが増している傾向にあります。SNSでの拡散が進むことでネットニュースにも取り上げられ、さらに話題化するとマスメディアに取り上げられる形で炎上が広がっていきます。
炎上事例から学ぶ|SNS炎上が起きた時の対処法
では、こうしたSNS炎上が起きた場合、どのように対応を行えば良いのでしょうか?
1. 事実・論調の確認と原因究明を行う
まずは事実確認を行いましょう。まずは、
- 何が原因で炎上しているのか
- そもそも事実なのか(偽情報ではないのか)
を見極めましょう。その上で偽情報(デマ)ではないと判断できた場合、
- ユーザーは何に対して批判しているのか
- ユーザーは企業に対して何を求めているのか(謝罪・説明など)
を読み解き、まずは原因究明に努めましょう。これらを行わないまま投稿を消してしまったり謝罪を行ってしてしまうと、論点のズレた対応をして、「事実を隠蔽しようとしている」「謝罪になっていない」など二次炎上を招く可能性もあります。
2. 迅速かつ冷静に方針を決定する
原因究明を行ったら、なるべく迅速に方針を決定しましょう。
- どのような声明をどこで出すのか
- ステークホルダーへの説明はいつどのように行うか
対応に関わるメンバーで協議し、迅速に対応を行うことが大切です。声明を発表するまでにも投稿は拡散し、事態は悪化し続けています。声明の発表が遅れたことで、さらなる炎上につながることもあるため、冷静さはもちろん素早い対応も必要になります。そのためにも、エスカレーションフローやガイドラインを作成しておくことをおすすめします。
3. メディアやステークホルダーへの誠実な対応を行う
実際に炎上が起きると、メディアからの問合せが増えるなど普段と状況が一変しますが、その中でも一貫性を持ち誠実に対応を行うことが大切です。対応や発信内容に一貫性が無かったり、対応が不誠実であったりするとさらに炎上が強まる可能性もあります。トラブル発生時に間違った対応をしないように事前の対策を進めておくようにしましょう。
SNS炎上を回避するための対策方法
ではここで、SNS炎上を回避するためにできる事前対策を5つご紹介します。
1. SNS運用ルールの策定
1つ目はSNS運用ルールの策定です。SNS運用担当による不適切投稿などが起こる原因として、社としてのルールが統一出来ておらず運用が属人化していることが挙げられます。SNSの投稿内容や運用ルールなどを統一化することで炎上の火種を防ぎ、炎上の発生リスクを最小限にすることができます。またルールには、炎上発生時の対応方法も明記するため、炎上時の初期対応も素早く行えるようになります。
2. コンテンツチェック体制を整える
SNSでの不適切投稿や広告・キャンペーンなどでの不適切表現は、社内のコンテンツチェックを手厚くしておけば防げたものも多いです。特に女性蔑視や男性蔑視、環境に関する問題、国籍に関する問題などが発端となって炎上に繋がるケースも多いため、性別・国籍・立場などが異なる視点から違和感がないかをチェックすることで炎上の火種を発見しやすくなります。
3. 従業員やSNS運用担当者のリテラシーを高める
従業員や公式SNSでの不適切な投稿は、従業員のSNSリテラシーを高める取り組みによって減らすことが可能です。社内でSNSリテラシー研修を行ったり、アルバイト・パート社員向けに短時間で学べるような動画を視聴してもらったりと、できることからリテラシーを高める取り組みを行ってみましょう。
4. 定期的にモニタリングを実施する
SNS上や、公式SNSでの投稿に対するコメントに炎上の火種がないかをチェックするSNSモニタリングも有効です。繰り返しになりますが、昨今は炎上拡散のスピードが増しているため、なるべく早く炎上を察知して対応できると損失も最小限にできます。目視でのモニタリングはもちろん、24時間体制の自動モニタリングを行うサービスも弊社では行っておりますので、リソースが足りないという場合には外部への委託も検討してみてください。
5. エスカレーションフローを整備する
エスカレーションフローとは、炎上などのインシデントが発生した際に、誰にどのような手順で問題を報告するかを決めた一連のフローのことを指します。炎上発生時などの緊急時に、どのように対応するかを定めておくことで、冷静かつ素早く対応を進めることができ、事態の悪化を最小限に留めることもできます。この時同時に、炎上時の一次対応なども定めておくと、現場の担当者が誤った対応をせずに済みます。
未然の対策で思わぬ炎上を回避しよう
本記事では、12の企業のSNS炎上事例を基に、SNS炎上の原因や影響、実際に炎上が起きた際の対処法や事前対策をご紹介してきました。炎上自体がエンタメ化している今、「ウチは大丈夫」といった慢心が思わぬ炎上を引き起こし、事態をさらに悪化させる原因となるかもしれません、今回ご紹介した対策をできることからぜひ実践してみてください。
弊社ではSNS炎上の対策や対応に関するセミナーを毎月開催しています。社内の体制や仕組み、業務の見直しに活かせる内容になっていますので、ぜひご都合に合わせてご参加ください。